正しい遺言の書き方|自筆証書遺言の要件と書き方の5つのポイント
この記事では、有効な自筆証書遺言の書き方と、遺言を書く上で重要なポイントを解説します。記入例(サンプル)や、なぜその…[続きを読む]
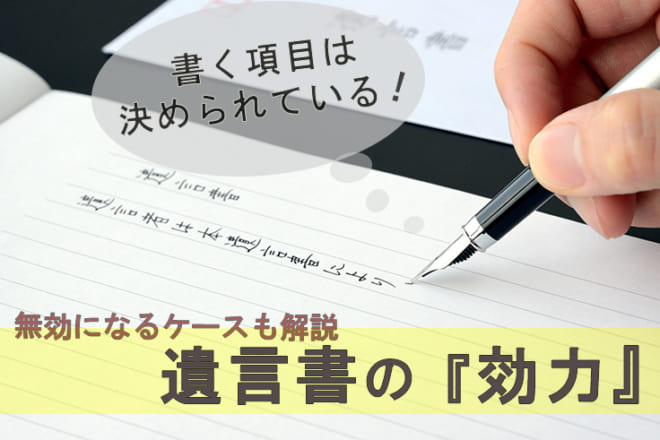
昨今、健康なうちから遺言書を書く方も増えてきましたが、そもそも遺言書というのは、どんな効力を持っているのでしょうか。
この記事では、遺言書の持つ効力について簡単にまとめた後、遺言書の効力が疑われる可能性のあるケースについても解説していきます。
目次
遺言書は、正しく書けば、強い法的な効力を持ちます。
遺言書がどんな効力を持つのか、詳しい話に入る前に、まずは「正しい書き方」について、知っておいていただきたいポイントが2つあります。
遺言書は、ただ書くだけでは効力を持ちません。
たとえば、最も利用数の多い自筆証書遺言(自分で書く遺言書)では手書きや署名押印が必須など、遺言書の書き方が法律で具体的に決まっています。
遺言書は、正しい書き方を守ってはじめて、効力を持つのです。
遺言書をのこせば、後世のことをなんでも決められると思っている方も、中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、遺言書にいろいろな記載をしたとしても、どんなことに法的な効力があるかは、民法で決められているのです。これを「遺言事項」といいます。
そこで2.からは、遺言書に書いたとき法的な効力を持つのはどんな項目なのか、具体的に見ていきましょう。
最も基本的な遺言書の役割といえるのが、財産に関する事項です。
誰がどの遺産をどのくらい相続するか、遺言書で定めることができます(民法902条、908条)。
相続分の指定として、何分の一や何割という割合で指定することもできますし、遺産分割方法として特定の遺産を誰々に相続させるという指定も可能です。
また、遺産を売却して金銭で分割する換価分割のような方法を指定することもできます。
遺言書のイメージとして一番に思いつく方も多いかもしれません。
遺言書では「遺贈」もできます(民法964条)。
遺贈とは、財産の全部または一部を無償で譲渡することです。
被相続人の死亡とともに自然的に発生する「相続」とは異なります。
相続では、配偶者や子などの相続人がどれだけ相続するか、原則として民法で決められています。
しかし、遺贈であれば「A不動産を親友Bに遺贈する」というように、相続人以外にも財産を渡すことができます。
ただし、遺贈によっても侵害できない「遺留分」というものがあるので、後述します(2-5)。
特別受益者とは、被相続人から贈与等を受けていたり、遺贈された人のことです。
たとえば、父親が死んだとき、子供2人の相続分は原則として平等です。しかし、父親が生前に弟を特別かわいがり、多額のお金をあげていたとします。
それなのに相続分が兄弟で同じだったら、兄にとっては不公平でしょう。
そこで、民法は特別受益者に対して受け取った利益分を相続分から控除するよう規定しています(民法903条1項)。
しかし、父親が遺言書に予め「弟に与えた特別受益は除外して遺産分割を行う」という旨を記しておけば、特別受益のことを考慮せずに遺産分割を行わせることもできます(民法903条3項)。
遺言書で、遺産分割を禁止することも可能です(908条)。
遺産分割禁止については、相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産分割を禁止することができます。
被相続人が死亡してすぐに遺産分割協議に入れば大きく揉めることが想定される場合には、一定期間置くことで、相続人が冷静になれる可能性があります。
遺言書で誰に何をどのくらい相続させるか指定できるのは前述のとおりですが、これには制限もあります。
「遺留分」という、相続人に最低限保障されている分け前についてまでは、遺言書で侵害することはできません。
つまり、遺言書に「1円たりとも息子には渡さない」と書きのこしたとしても、民法で「遺留分」として定めれている分については、たとえ被相続人の意思であっても、奪い取ることはできないのです。
遺言書で相続人を指定するだけではなく、廃除することもできます(893条)。
「廃除」とは、本来相続権のある人物を、相続関係から除外することです。
たとえば民法上、配偶者には必ず相続する権利が与えられていますが、生前配偶者に家庭内暴力を受けていたとしたら、相続なんてさせたくないですよね。
このように相続人に著しい問題があった場合には、遺言書で相続人から相続権を剥奪することが可能です。
ただし、廃除の条件は厳格に規定されています。
遺言書によって、結婚していない状態で生まれた子どもの認知(自分の子供だと認めること)もできます(781条2項)。これによって隠し子が発覚するケースも少なくありません。
新たに子どもの存在が判明したら、相続人が増えることになりますから、必然的に相続の内容も変わってしまいます。
なお、遺言書によって子どもの認知があった場合、遺言執行者は、就任から10日以内に認知の届け出を行う義務があります(「遺言執行者」については下記)。
相続人が複数いる場合、みんなで一緒に相続手続きを行うのは大変です。
下手に分担をしたら、誰がなんの手続きを行っているかわからなくなって、余計に手間がかかることも考えられます。
そこで、円滑に遺産分割を行うために、「遺言執行者」を選び、委託することができます(1006条1項)。
未成年の子供を育てる片親の方は、もし自分に万が一のことがあったら、子どものことが心配ですよね。
そこで、未成年者の子どもについて、自分が死んだら誰に面倒をみてもらうか(後見人になってもらうか)、遺言書で指定することができます(839条1項本文)。
未成年後見人をさらに監督する、未成年者後見監督人を指名することもあります(848条)。
特に離婚による片親の場合は、どうしても元夫や元妻に親権を渡したくないということもあるでしょう。
その場合、ご自分が亡くなったとしても親権が自動的に元配偶者に移るわけではありませんが、未成年後見人を指定しておくことがおすすめです。
同一人物がのこした遺言書が複数ある場合、日付が新しいものが優先されます。
つまり、新しい遺言書をのこすことで、前に書いた遺言書について撤回できます(1022条)。
遺言書は、何度も書き直して内容をアップデートしていくことができるのです。
上記の他にも、遺言書で法的な効力を有する事項は複数あります。
そんな遺言書ですが、遺言書自体の効力がなくなってしまう可能性もあるのです。
遺言書には3種類ありますが、いずれにせよ形式が法律で定められています。
たとえば、最もポピュラーな自筆証書遺言(自分で書く遺言書)は、手書きでなかったり、押印や署名を忘れていたりと、形式不備の場合には無効になる可能性が高いです。
せっかく残す遺言書が無効にならないためにも、きちんと弁護士に正しい形式を教えてもらいましょう。
形式不備などが原因で遺言書が無効になるパターンについては以下の記事をお読みください。
認知症の被相続人が書きのこした遺言書はどうでしょうか。
遺言書が効力を発するためには、書いた当時に「遺言能力」が必要になります(963条)。
遺言能力とは、自分本来の意思によって、自分が一体何を書いているのかしっかり認識しながら遺言書を書くだけの能力があるかどうか、ということです。
認知症の状態で書いた遺言書の効力が認められるかどうかは、認知症にもレベルがありますから、一概にはいえません。
軽度の認知症であれば、「遺言能力がない」とまではいえず、遺言書の効力が認められることがあります。
反対に、重度の認知症など、判断能力が十分になかったという証拠があれば、無効になってしまう可能性が高いです。
遺言書が後世で無効にならないためには、遺言書を書いた当時に判断能力があったと証明するため、医師に診断書をもらっておきましょう。
また、公証人の協力のもと作成するという点で自筆証書遺言よりも信頼性が高いので、公正証書遺言にするのもおすすめです。
今回みたように、遺言書には様々な効力がありますが、法的効力を有する項目については法律で定められています。
また、法的効力のある項目に関する記載であったとしても、法定の形式を守らなかったり、書いた当時に病気の疑いがあったりすると、遺言書自体の効力が失われてしまいます。
せっかく遺言を残すなら、正しい効力を発揮して、自分の意思を後世に伝えていきたいですよね。
「〇〇について書きたいけれど、法的な効力はあるのか?」
「自分の遺言書が無効にならないためにはどうしたらよいのか?」
など、遺言書に関するお悩みは様々です。
遺言書を自分で書く前に、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。